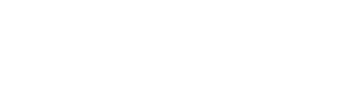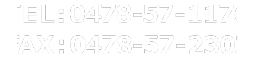弘法大師
弘法大師
真言宗は、弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)(774~835)によって開かれました。
その教えは、自分自身が本来持っている「仏心(ぶっしん)」を、「今このとき」に呼び起こす即身成仏(そくしんじょうぶつ)に求められます。それは、自分自身を深く見つめ、「仏のような心で」「仏のように語り」「仏のように行う」という生き方です。
この教えをもとに、人々がともに高めあっていくことで、理想の世界である密厳仏国土(みつごんぶっこくど)が実現します。


 ご本尊
ご本尊
真言宗のご本尊は大日如来(だいにちにょらい) です。
大いなる智慧(ちえ)と慈悲(じひ)をもって、すべてのものを照らす根本の仏さまです。
また、仏教に多く存在する仏さますべてを、ひとつも否定することなく、それぞれを大切に考えます。
すべての仏さまは大日如来につながると考えます。
そのため真言宗寺院のご本尊はさまざまです。
 密教の祖師
密教の祖師
密教はインドで成立し、中国を経て弘法大師(こうぼうだいし)によって日本に伝えられました。弘法大師を含め八人のお祖師さまがおり、八祖(はっそ)として尊崇(そんすう)しおまつりしています。真言八祖には、「付法の八祖」と「伝持の八祖」の二通りがあります。付法の八祖は、大日如来(だいにちにょらい)、金剛薩埵(こんごうさった)、龍猛菩薩(りゅうみょうぼさつ)、龍智菩薩(りゅうちぼさつ)、金剛智三蔵(こんごうちさんぞう)、不空三蔵(ふくうさんぞう)、恵果和尚(けいかかしょう)、弘法大師をいい、秘密法流の正系(せいけい)(灌頂受法の相承)を示します。
伝持の八祖とは、龍猛菩薩、龍智菩薩、金剛智三蔵、不空三蔵、善無畏三蔵(ぜんむいさんぞう)、一行阿闍梨(いちぎょうあじゃり)、恵果和尚、弘法大師をいい、歴史的に密教の伝持弘通(でんじぐずう)(経典儀軌の相承)に努められたお祖師さまです。伝持の八祖像をみると、龍猛菩薩は三鈷杵(さんこしょ)、龍智菩薩は梵経(ぼんきょう)、金剛智三蔵は念珠を持ち、不空三蔵は外縛印(げばくいん)、善無畏三蔵は右手の人指し指を立て、一行阿闍梨は衣の袖下で印を結び、恵果和尚は童子を伴い、弘法大師は五鈷杵(ごこしょ)を持っておりますので、そのお姿や持ち物によって見わけることができます。

付法の八祖と伝持の八祖
歴 史
弘法大師によって開かれた真言宗は、東寺(とうじや)高野山(こうやさん)中心に広められます。その後、平安の末期に興教大師(こうぎょうだいし)覚鑁上人(かくばんしょうにん)によってさらに新しい力が吹き込まれると、紀州に根来寺(ねごろじ)が創建されました。
鎌倉時代になり、頼瑜僧正(らいゆそうじょう)によって新義真言の教えが成立しました。宗団は根来寺を中心に栄えましたが、戦国時代の戦渦により、専誉僧正(せんよそうじょう)をはじめ多くの僧侶が根来寺を離れることになりました。
その後、豊臣秀長公によって奈良の長谷寺(はせでら)に招かれた専誉僧正は豊山派をおこし、長谷寺は学山として栄えました。豊山派の派名は長谷寺の山号「豊山(ぶさん)」に由来します。

真言宗豊山派総本山長谷寺
江戸時代、五代将軍 徳川綱吉(とくがわつなよし)公の生母である 桂昌院(けいしょういん)が音羽(現文京区)に護国寺を建立し、豊山派の江戸の拠点として末寺を増やしました。

真言宗豊山派大本山護国寺
現在は、全国に3,000カ寺、僧侶数5,000人、檀信徒数200万人をほこる、真言宗有数の宗団となっています。
宗 紋

真言宗豊山派の宗紋である「輪違(わちがい)」は仏さまと私たち衆生(しゅじょう)は、もとは同じで異なることはない“ 凡聖不二(ぼんじょうふに)”という教えをあらわしています。